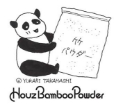竹パウダーの消臭・調湿効果
1. 化学反応型
臭いの原因となる分子と化学反応を起こし、無臭の物質に変化させます。
例:重曹(炭酸水素ナトリウム)は酸性の臭い成分と中和反応を起こして消臭。
2. 吸着型
活性炭やゼオライトなどが臭い成分を物理的に吸着して除去。
吸着された分子は空気中から取り除かれることで、匂いが感じられなくなります。
3. マスキング(香料)型
強い香りで臭いを覆い隠す方法。
実際には臭いは除去されていませんが、人間の鼻では感じにくくなるようにします。
4. 分解(酵素)型
酵素やバクテリアを利用して、臭いの原因物質を分解して消す仕組み。
ゴミ処理やペット用消臭剤などによく使われます。
5. 中和型(酸・アルカリ)
臭い分子が酸性かアルカリ性かによって、反対の性質の物質と混ぜて中和する。
これはトイレの消臭剤や台所周りでよく活躍します。
調湿の主なメカニズム
1. 湿度の吸放出(調湿)
素材が空気中の湿気を吸収したり放出したりすることで、湿度を安定させる仕組み。
例:珪藻土・漆喰・木材などの自然素材が持つ多孔質構造により、湿度変化に反応。
2. 温度の調整(熱の蓄積・放出)
壁材や床材が熱を蓄えておいて、時間差で放出することで室温を均一に保つ。
蓄熱性の高い素材(厚みのある土壁など)が効果的。
3. 換気との連携
調質は、単独ではなく換気や空気清浄と組み合わせて機能することが多い。
自然換気を利用したパッシブデザインでは、風の通り道や日射取得により調質効果が高まる。
4. 自動制御型(機械式)
エアコンや除湿機などがセンサー情報をもとに温度・湿度を制御する。
スマートホームではAIが学習して、より効率的に調質することも。
竹パウダーの消臭は、吸着タイプ 調湿は竹が持つ多孔質構造により、湿度変化に反応
何れも竹が多孔質で、且つパウダー状に粉砕してある事でその表面積は莫大になり
能力が増大します。
竹炭もいいですが、炭化するのに二酸化炭素を発生させます、竹パウダーなら二酸化炭素の発生も少なく、上記の様にしたらちょっとおしゃれかな?